自己破産で退職金はどうなる?自己破産にはメリットも
借金の返済に困っている人が、最後に取る手段が自己破産です。これは、現在の借金を返済する能力が自分にはないということを裁判所に申し立てて、認めてもらうことで返済を免除してもらうというものです。ただし、その際に保有している財産や預貯金などがあれば、その分は返済しなくてはいけないのです。
実は、この財産には退職金も含まれます。現在退職して既に退職金を受け取っている人はもちろんですが、まだ働いている場合でも退職金を請求できる権利が財産として扱われるのです。ただし、その全額が債権者に配当されてしまう、という訳ではありません。
自己破産をすると、持ち家や車を失ったり、ブラックリストに入って借金ができなくなったりするというデメリットがあります。そのために、手続きをためらっている人もいるでしょう。しかし、手続きをしてしまえば今後の返済が免除され、もう一度人生をやり直すことができるのです。その際も、一部の財産は手元に残すことができるので、全くのゼロからスタート、という訳でもありません。
この記事では、自己破産をしたときの退職金の扱いや、自己破産のメリットについて詳しく解説していきます。
自己破産とは
自己破産というのは、個人が行う破産手続きです。借金をして、その返済ができなくなった場合に利用される制度で、裁判所に破産申立をして認められた場合に、その返済を免除してもらうことができるのです。
この制度を利用する場合は、まず自分が支払不能の状態だということを裁判所に申し出て、それを認めてもらわなくはいけません。その際は、本当に返済ができないのか確認されます。現在の借金の額や返済状況、収入、財産などの情報を集めた上で、裁判所が判断するのです。
ただし、自己破産は厳密にいうと、借金がなくなるわけではありません。返済が免除になる、免責の許可を得られる制度です。また、免責にはならない借金もあるので注意しましょう。
同時廃止と管財事件の違い
自己破産には、大きく分けて2種類あります。管財事件と同時廃止事件があるのですが、借金の状況や、財産をどれだけ保有しているのかによって、分けられるのです。その違いについて、解説していきます。
・管財事件
保有している財産が一定額以上の場合や、自己破産に至った借金に問題がある場合、この手続きをされます。例えば、ギャンブルが原因で借金をすることになったなど、自己破産を認めるかの確認が必要な場合です。財産が一定以上ある場合は、一定額を残して没収されます。さらに、破産管財人に支払われる報酬として事前に予納金を裁判所に納めなくてはいけません。
・同時廃止事件
財産がほとんどなく、債権者に対して特に分配するものがない場合は、この手続きを行います。破産管財人が必要ないので報酬が必要なく、財産の調査や分配なども行われないので手続きにかかる時間も短く、費用も他の手続きよりかなり安く済みます。
どちらの手続きになるかで、費用や期間も大きく異なります。しかし、個人の場合は特に高額な財産や複雑な債権がない限り、ほとんどが同時廃止事件になるでしょう。
自己破産と退職金の関係
自己破産をすると、自由財産といわれる分を手元に残しておくことはできますが、それ以上の財産などは処分して債権者に配当を行わなくてはいけません。そのとき、退職金がどうなるのか、という点は気になる方も多いでしょう。
退職金というのは、会社に現金を預けているわけではありません。会社に対して、請求する権利があるというものです。つまり、会社に対して持っている債権という扱いになるのです。
自己破産においては、債権も財産の一種として扱われます。つまり、退職金に関しても今すぐ請求するべきものとなります。ただし、そのためには退職しなくてはいけないので、その後の生活に影響が出てしまうでしょう。
そのことを踏まえて、退職金はまず現在の段階でもらえる金額を計算します。そして、4分の3は差押禁止財産なので、4分の1だけを財産として計上します。その際、退職してまで受け取るというのは難しいため、さらにその半分の8分の1だけを計上することになっているのです。
さらに、8分の1で20万円以下になった場合は、全額を自由財産にすることができます。実際に、4分の1になるか8分の1になるかは、裁判所の判断によります。大抵の場合は、8分の1になることが認められるので、安心してください。
退職金は受け取る時期で差し押さえ額が違う
退職金についての扱いは、その退職金をいつ受け取ることになるのかによって、差し押さえられる額が変わってきます。どのくらいの期間ならどのくらい差し押さえられるのか、その計算方法等を解説します。
ちなみに、これは会社に退職金制度があることを前提としています。その制度がない場合は、そもそも問題にはなりません。
退職金を受け取るまで期間がある場合
現在会社に勤めていて、退職金を受け取るのはまだ先という場合は、現段階で退社した場合に受け取ることのできる退職金の額を基準として計算します。そのとき、退職金見込み額を全額差し押さえられるわけではありません。
退職金は、会社に請求できる権利を持っているものとして扱われるので、債権という扱いになります。そして、退職金債権については、4分の3が差押禁止債権と定められています。つまり、残りの4分の1に関しては、差し押さえることが認められるのです。
ただし、破産手続き中に退職する予定はない、という場合は、退職金を受け取るのが困難です。その上で退職金を得るには、本人が実際に退職するか破産管財人が会社に前払いしてくれるように請求しなくてはいけません。そうなると、破産したことが会社に知られてしまい、今後の仕事に支障が生じることもあるでしょう。また、退職金を受け取るのが将来のことなので、満額受け取ることができるかどうかは不確かです。もしかしたら、その前に会社が倒産するなどして、受け取れなくなる可能性もあるのです。
そのため、裁判所の判断にもよるのですが、困難な点を踏まえて本来の差し押さえ額のさらに半額となる、8分の1だけを退職金相当額として支払えばいい、とされるのが一般的です。さらに、退職金が160万円未満なら納めるべき金額はその8分の1の20万円未満になります。その場合は、全額を自由財産として認められるケースがほとんどです。
つまり、退職金が現段階で160万円未満なら差し押さえられることはなく、さらにそれ以上の金額であっても、8分の1だけ差し押さえられて残りは自由財産の扱いになる、ということです。例えば退職金が現段階で200万円になる予定であれば、その8分の1である25万退職金相当額として、処分される財産に含めればいいのです。
注意したいのが、計算する時の基準となる退職金の額は満額ではなく、あくまでも現段階での退職金という点です。自己破産後も、その会社に勤め続けるのであれば、その差額分の退職金はそのまま受け取ることができるのです。
退職金の受け取り時期が近い場合
退職金の受け取り時期が近い場合、もしくは破産手続き中に退職するという場合は、近日中に退職金を確実に受け取ることができます。その場合は、原則に従って4分の3が差押禁止債権となり、4分の1が差し押さえの対象になります。
すでに退職金を受け取っている場合
既に退職金を受け取っている場合は、それが現金として残されていれば現金として扱い、預貯金口座に入金されていれば預貯金として扱われます。どのような経緯で入手した者かに関係なく、通常と同じように扱われるのです。そのため、現金なら99万円を超えている場合、預貯金なら金額が20万円を超えている場合に、財産として清算される対象になってしまいます。
その他退職金が自由財産として認められる場合
一般的な退職金が自由財産として認められるケースについては、上記のとおりです。では、その他退職金が自由財産として認められるのは、どのような場合でしょうか?
中小企業退職金共済制度と小規模企業共済制度
企業によっては、会社から直接退職金を支払うのではなく、中小企業退職金共済や小規模事業共済を利用して退職金を支払います。前者は、中小企業退職金共済法という法律に基づいて設けられている退職金制度で、後者は中小機構という国の機関によって運営されている退職金制度です。
これらによって受け取ることができる退職金は、法律では「本来的自由財産」という扱いをされています。そのため、破産手続きをしても没収されることはないのです。同じ退職金でも、一般的なものとは異なるものとして扱われます。
破産財団に組み入れる
通常、退職金は会社を辞める予定がない限り、その8分の1相当額を財産評価額にカウントします。その退職金を破産財産に組み入れてしまうと、自由財産拡張の対象に出来るのです。自由財産拡張というのは、本来20万円以上の財産は処分することになるところを、合計99万円までなら残してもいいものとする、という制度です。
退職金は、金額に関わらず元々8分の7は自由財産として扱われます。そのため、他の財産と退職金の8分の1を合計して99万円以下なら、手元に全額を残すことができます。
本来、この自由財産の拡張を認めてもらえるかどうかは、破産管財人の意見が必要とされています。つまり、破産管財人がいない同時廃止事件の場合は、認められないことになってしまいます。その場合は、裁判所で定めた自由財産拡張基準に沿ったものであれば破産管財人がいなくても認められます。しかし、基準にないものについては認められないので注意しましょう。
自己破産のメリットとデメリット
自己破産によって生じるメリットやデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?その具体的な内容について、解説します。
自己破産のメリット
まずは、メリットについて解説します。大きなメリットとしては、以下の3点があります。
・全ての債務の支払い義務が免除される
・破産手続きを開始してからは、強制執行の心配がない
・一定の財産を残すことができる
・全ての債務の支払い義務が免除される
自己破産を司法書士等の専門家に依頼することで、借金の取り立てがストップします。そして、申請して免責許可が得られれば、今ある債務は全て返済が免除されるのです。そのため、依頼した時点で借金の返済に悩まされることはなくなり、免責許可を得られれば借金からは完全に開放されます。
・破産手続きを開始してからは、強制執行の心配がない
借金の返済が滞ると、債権者によって裁判を起こされて給料を差し押さえられることがあります。しかし、自己破産の申立をして裁判所から破産手続きの開始決定が出されると、強制執行手続きは全て停止になります。そうなると、既に差し押さえられている給与等も差し押さえが解除され、全額を受け取れるようになるのです。
・一定の財産を残すことができる
自己破産をするとすべての財産がなくなると思われがちですが、実は自由財産と言われる最低限の財産は残すことができます、具体的には、99万円以下の現金や20万円以下の財産は残しておくことができるのです。そのため、家具や家電、衣類などのほとんどは残すことができるでしょう。
自己破産のデメリット
では、デメリットとしてはどういった点が考えられるでしょうか?主なデメリットとなるのは、
・保証人がいる債務に関しては、返済の請求をされてしまう
・信用情報のブラックリストに登録される
等があります。もう少し詳しく、その内容を解説します。
・保証人がいる債務に関しては、返済の請求をされてしまう
借金の中には、保証人や連帯保証人が設定されているものがあります。そのような借金は、返済の免除を得た時にそちらへと請求されてしまいます。なぜなら、免責はあくまでも借金の返済をしなくてもいいというだけなので、借金そのものがなくなるわけではないからです。保証人などには、自己破産をすることをあらかじめ伝えておいた方がいいでしょう。
・信用情報のブラックリストに登録される
信用情報機関のブラックリストに登録されてしまうので、それ以降は新たな借金をすることやクレジットカードを発行すること、ローンを組むことが難しくなります。ほとんどの業者では、ブラックリストに入っていると契約を断るでしょう。
ブラックリストには、いつまでも入っているわけではありません。最低でも5年、一部の信用情報機関には10年登録されてしまいます。それ以降であれば、再び消費者金融やクレジットカードを利用できる可能性はあります。
自己破産をすることで、このようなメリット・デメリットが生じます。中には、デメリットが気になる人もいるでしょう。しかし、借金を放置しておくといつまでも利息が増えてしまい、返済がどんどんと困難になってしまいます。そのため、デメリットについて気にするよりも、早めに借金の返済を免れることが重要なのではないでしょうか。
自己破産を申請する流れ
自己破産の申請は、どのような流れで行われるのでしょうか?また、申請するにはどのような書類が必要になるのでしょうか?
自己破産に必要な書類
自己破産に必要な書類というのは、現在の収入に関するものや保有している財産を証明するものが中心です。具体的には、
・申立書
・陳述書
・債権者一覧
・住民票・戸籍謄本
・申立を行う直前2~3カ月分の給与明細
・保有しているすべての銀行口座の取引記録
・1~2年分の源泉徴収票、課税証明書、もしくは非課税証明書
・財産目録
・過去1~3か月分の家計簿及び公共料金領収書
の9種類が最低限必要です。それ以外にも、以下の書類で当てはまるものがあれば、用意しなくてはいけません。
・退職金に関する書類
・加入している保険についての資料
・すべての賃貸借契約に関する契約書
・確定申告をしている場合は、過去1~2年ぶんの確定申告書及びその資料
・保有する自動車に関する資料
・保有する不動産に関する資料
・株・FXなどをしている場合はそれに関する資料
自己破産の申請の流れ
具体的な自己破産手続きの流れについて、確認してみましょう。手続きは、このような流れで行われます。
(1)司法書士等の専門家に依頼する
自己破産する場合、まずは専門家である司法書士等に相談するところから始まります。自分で手続きをすることもできますが、複雑なところもあり専門的な知識がなければ難しいので、専門家に依頼したほうが無難でしょう。
ただし、どの事務所でもいいわけではありません。それぞれ専門にしている分野があることも多く、どこでも借金問題に明るいというわけではないのです。自己破産を含めた、債務整理を得意とするところをインターネットなどで探してみましょう。
相談にいくと、現在の借金の状況やおおよその収入、支出および保有している財産などを確認されます。状況によっては、自己破産ではなく別の債務整理の方法を勧められることもあります。
(2)依頼を受けてもらい、受任通知が送付される
依頼すると、司法書士等の専門家から債権者に対して、受任通知が送られます。この受任通知が送られると、その手続をしている間は借金の取り立てがなくなります。そのため、精神的な負担からも解放されます。
(3)申立に必要な書類を作成する
裁判所に申立を行う際は、上記の書類を提出します。基本的には司法書士等が作成するのですが、こちらで必要な資料等を用意するものもあります。裁判所に申立を行ってしまえばそれほど自分でやることはなくなるので、この書類作成が最も難しいといえるでしょう。
(4)裁判所に申立書を提出し、自己破産手続きの開始決定
無事に書類を作成したら、裁判所に提出します。裁判官と面接を行い、自己破産をすることになった理由などを説明しなくてはいけません。
面接の結果と、提出された書類に問題がなければ自己破産手続きの開始決定が裁判所から出されます。同時廃止事件ならすぐに免責手続へと移行するため、スピーディーに進みます。
管財事件となった場合は、裁判所で管財人を選出します。その後、管財人が財産を管理して債権者集会を開き、配当を行う等の手続きをしてから免責手続きへと移行します。そのため、同時廃止事件と比較してかかる期間は、半年前後長くなります。
自己破産の申請費用
自己破産の申請に必要な費用は、その手続が同時廃止事件と管財事件のどちらになるかによって、大きく異なります。その費用は予納金として裁判所に納めるのですが、それぞれの目安としては以下のような金額になります。
| 同時廃止事件 | 管財事件 | |
|---|---|---|
| 必要な費用 | 1万円~3万円 | 50万円~ |
予納金には、手数料1,500円(収入印紙で納付)と最低3,000円の郵券費、官報公告費と破産管財人への報酬が含まれます。同時廃止事件の場合は、破産管財人報酬は不要です。
この費用は、もし専門家に依頼せず自分で手続きするとしても、必ず納めなくてはいけません。専門家に依頼する場合は、これとは別に依頼料が発生します。
予納金は、基本的に一括で支払います。しかし、裁判所によっては分割での支払いを認めているところもあります。その場合は、裁判所が指定する回数で支払わなくてはいけません。
免責不許可となった場合の対処法
免責不許可になってしまった場合は、どう対処するべきでしょうか?
まず行うべきなのが、即時抗告の申立です。免責不許可の通知を受けてから一週間以内に行う手続きで、抗告審が行われます。そこで主張が認められれば、免責が認められるのです。
しかし、認められる可能性はかなり低いのです。その場合は、改めて個人再生か任意整理のどちらかの手続きを検討しましょう。
自己破産の免責が不認可になるケース
自己破産には、免責不許可事由というものがあります。そのいずれかに該当するケースでは、免責が不認可になってしまうのです。
免責不許可事由に該当する主な事項は、以下のようになっています。
・債権者(貸主)を害する目的で自分の財産を隠匿する、あるいは不利益な処分をした場合
・一部の債権者にだけ支払いをしていた等、債権者平等ではなく不平等にしていた場合
・著しく財産を減らしたり、過大な借金をしたりすることとなった原因がギャンブル等の浪費である場合
・破産を申立する1年前から破産手続き開始決定が出るまでの間に、破産しそうなのを知っていながら虚偽の申請をして信用取引により財産を得た場合
・業務や財産の帳簿、書類を隠匿、あるいは偽造した場合
・裁判所に提出した債権者名簿に、虚偽の情報が含まれていた場合
・裁判所の調査を拒む、あるいは虚偽の説明をした場合
・破産管財人などの業務を妨害した場合
・過去に一度、破産や再生の申立をして、確定してから7年経っていない場合
・その他、破産法に定める義務に違反した場合
免責不許可となった場合の対処法
免責不許可になってしまった場合は、どう対処するべきでしょうか?
まず行うべきなのが、即時抗告の申立です。免責不許可の通知を受けてから一週間以内に行う手続きで、抗告審が行われます。そこで主張が認められれば、免責が認められるのです。
しかし、認められる可能性はかなり低いのです。その場合は、改めて個人再生か任意整理のどちらかの手続きを検討しましょう。
自己破産の年間の申請人数
自己破産の年間の申請件数は、2018年が約73,000人でした。人数が最も多かった2003年には約240,000人が申立をしていたので、それよりはかなり少なくなっています。しかし、2015年の時点ではさらに少なく、約64,000人でした。そこから銀行カードローンの利用者数増加やその枠の縮小、消費者金融等のサービス向上、キャッシュレス化推進など、様々な変化が起こっています。そのような背景もあって、自己破産の人数は毎年少しずつ増えているので、今後も増加が続くかもしれません。
自己破産の免責が許可になる割合
自己破産を申請してもなかなか認められない、というイメージがある人は多いのですが、実はそんなことはありません。自己破産を申請した人のうち、97%近くは免責が認められているのです。つまり、不許可になってしまう割合はわずか3%、30人に1人しかないのです。
これには、まず免責不許可事由として免責にならないケースが明確になっているのもその理由の一つです。また、たとえ免責不許可事由に該当する場合であっても、悪質と判断されない限りは裁量免責として許可を得られるケースが多いのです。
自己破産に関する誤解
自己破産に関しては、様々な誤解をしていることもあります。ここでは、誤解をしている人が多い点について、正確にはどのような内容なのかを解説していきます。
引っ越しや旅行ができなくなる
自己破産の申出をしたときに、裁判所には住所を届け出ます。破産手続きの開始決定が出されたあとは、その住所からの転居は禁止されるのです。また、長期旅行もできなくなります。
これは、破産申告をしてから逃亡したり、もしくは財産を隠そうとしたりすることを防ぐのが目的です。また、破産管財人がいるときは、調査のために連絡を取ることがあります。その連絡が取れなくなると困るので、それを防止するという意味合いもあります。
もし、どうしても引っ越しや長期旅行の必要があるときは、裁判所に許可を取らなければいけません。
ただし、同時廃止事件の場合は、免責決定前でも引越しや長期旅旅行に制限はないので、裁判所の許可も必要ありません。引越しをしたときは、裁判所に新しい住所を申告してください。
すべての財産が処分される
根こそぎ財産が失われると思っている人もいますが、一部の財産は手元に残しておくことができます。その分は自由財産といわれ、価値が20万円以下の財産や99万円以下の現金については、手元に残してその後の生活のために使うことができます。車も、評価額が20万円以下であれば手放さずにすみます。
年金が受け取れなくなる
年金には、大きく分けて公的年金と私的年金の2種類があります。国民年金や厚生年金は、公的年金に該当します。保険会社の個人年金や企業が独自に行う年金制度の企業年金は、私的年金です。このうち、公的年金は差押禁止財産や新得財産という扱いになり、自己破産をしても手元に残しておける自由財産に含まれます。そのため、問題なく受け取ることができるのです。
私的年金のうち、企業年金も差押禁止財産に含まれます。企業によっては、退職金の代わりとしていることもあるのですが、その場合でも問題なく受け取ることができます。
受け取ることができないのは、保険として加入する個人年金だけです。これは、解約時に返戻金がある保険と同じように、財産として扱われます。より詳しい条件としては、解約した場合の返戻金が20万円を超えるようなら処分対象になるのです。既に受給していても、解約すれば返戻金を受け取ることができるため、その額が20万円を超える場合は解約しなければいけません。
自己破産は専門家に相談がおすすめ
個人で自己破産をする場合、必ずしも専門家に相談する必要はありません。しかし実際には、専門家に依頼して手続きをするべきです。それは、費用以上のメリットがあるからです。司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合、自分で手続きを行う場合の違いを表にまとめたので、比較してみましょう。
| 司法書士 | 弁護士 | 自分で行う | |
|---|---|---|---|
| 書類作成代行 | ◎ | ◎ | × |
| 申立手続き代行 | × | ◎ | × |
| 交渉等の代理人 | × | ◎ | × |
| 費用 | 〇 | × | ◎ |
| 少額管財事件 | × | ◎ | × |
| 取り立て・督促 | ◎ 依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる | ◎ 依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる | × 交渉が終わるまでは止まらない |
受任通知を送付して、借金の督促が止まるのは司法書士等の専門家に相談したときだけです。自分で手続きをする場合は、手続きが終わるまで取り立てに耐え続けるしかありません。
司法書士と弁護士の大きな違いは、管財事件になるときに少額管財事件へと変更できるかどうか、という点です。これは弁護士しかできないのですが、同時廃止事件であれば問題ありません。また、少額管財事件を認めていない裁判所も多いので、所轄の裁判所次第ではその違いもなくなります。
自己破産において、最も重要なのが書類の作成です。それを代行してくれる以上、依頼するのが司法書士でも弁護士でも、そこまで大きな差はありません。自分で手続きをするとなると、その書類も自力で作成しなくてはいけないのです。
専門家への依頼は費用もかかりますが、それ以上のメリットがあるのです。
自己破産の相談実績
では、実際に当事務所で自己破産の相談を受けた実績について、紹介します。
ケース① 50代男性
・職業 会社員
・借金総額 1000万円
Aさんはかつて、両親ががんになったために医療費で借金をしていて、自己破産をしたことがありました。それから10年が経過して、車が故障したことで自動車ローンを組み、クレジットカードも持っていました。しかし、最近になって会社をリストラされてしまい、退職金400万円を受け取って無職になりました。その際に、ショックのあまりうつ状態になってしまい体調も崩したため、仕事ができない状態が長く続いていました。その結果、退職金も使い切って借金をして生活していたのです。
その後、精神的に回復してきたことで仕事を探したかったのですが、その前に膨れ上がった借金の返済をどうにかしたいと思い、自己破産をしようと考えたのです。
すでに1度自己破産をしているので、2度目ができるのかと不安に思ったまま相談にいらっしゃったのですが、自己破産には回数制限がないということを説明すると安心していらっしゃいました。借金の理由にも免責不許可事由に該当するような点がなかったので、無事に手続きは進み免責許可が出されました。
ケース② 40代男性
・職業 派遣社員
・借金総額 300万円
独身のまま派遣社員として働いていたのですが、仕事が少ない時期がありその間は銀行のカードローンや消費者金融から借り入れて生活費に充てていました。しかし、最近になって派遣切りにあってしまい、失職してしまったのです。それからしばらくして正社員として働ける仕事を見つけたのですが、それまでの間に生活費を借りていたため、限度額いっぱいになるほど借金が増えていたのです。正社員になれば返済できると思っていたのですが、見つけた仕事はそれほど給料が高くありません。そのため、返済によって生活が困窮するのは確実です。そこで、自己破産をして借金をリセットしようと思い立ったのです。
借金の理由にも免責不許可事由に該当するものはなく、特に財産もないことから同時廃止事件として、問題なく手続きが進められました。
まとめ
・自己破産には、同時廃止事件と管財事件がある
・自己破産の際、退職金は財産として扱われることがある
・退職金のうち、4分の3は差押禁止財産なので、4分の1だけが財産として扱われる
・退職金の計算は、現時点で退職した場合にもらえる金額を基準に計算する
・退職の予定がない場合は、8分の1だけを財産として扱う
・自己破産をすると、借金の返済義務がなくなる
・事故情報が記録されてブラックリストに入るが、5年から10年ほどで記録は消える
・自己破産をするには、裁判所に申請費用を納めなくてはいけない
・司法書士等の専門家に依頼する場合は、別途依頼料が必要
・免責不許可事由に該当する場合は、免責が認められない
・免責が認められなかった場合は、他の債務整理を検討しよう
・自己破産をすると、引っ越しができないなどの誤解をしている人が多い
・申請の際は、費用が掛かっても専門家に依頼するのがおすすめ






















pixta_87801584_S.jpg)


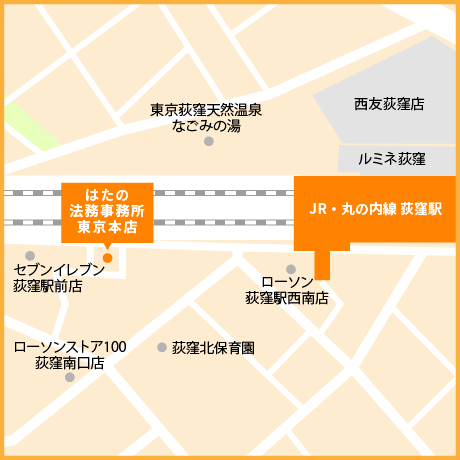
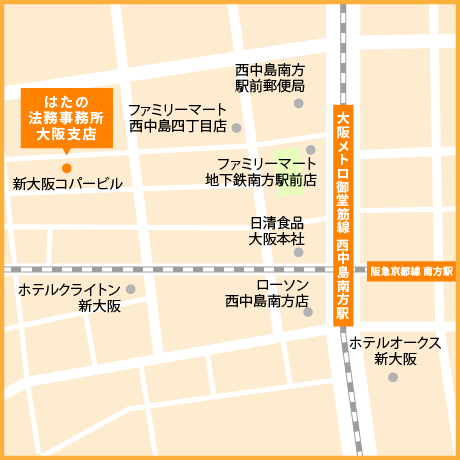







クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。