利息制限法とは?上限金利や改正前の契約はどうなる?計算例などをわかりやすく解説!
過払い金に深く関わりがある、利息制限法をご存知でしょうか?
利息制限法は、借金をした際にかかる金利に関して、その上限を定めている法律です。消費者金融や銀行などの金融機関は、この法律で定められた金利の上限を超えて貸し付けることは禁止されています。その上限は貸付金額によっても異なりますが、最大でも年20%となっています。また、返済が遅れた際に発生する遅延損害金についても、その利率の上限を定めています。この法律は、貸主が過剰な金利を設定して暴利をむさぼり、消費者を搾取することを防ぐために定められています。
利息制限法を超える金利がかけられて返済していた借金に関しては、遡って適法範囲の金利で計算し直す引き直し計算をして、払い過ぎた分については返還を求めることができます。払い過ぎた分が、過払い金にあたります。
この記事では、利息制限法と引き直し計算、上限金利を超えた契約はどうなるのかを解説します。
利息制限法とは何?
利息制限法という名前を聞いた事がある人は多いでしょう。しかし、その詳しい内容については良く知らないという人もいると思います。まずは、利息制限法について詳しく解説します。
そもそも利息とは?
利息、もしくは利子というのは、お金を貸し借りする際にその金額に対し、一定の割合で支払われることになる対価のことをいいます。借りたお金をそのままの金額で返済する場合は、利息が発生していません。また、約束もなく利息が発生することもありません。いくら借りて、いつまでにいくらにして返すのかという約束があって、初めて利息が発生するのです。
ちなみに、利息と似た言葉で金利というものがあります。利息の場合は具体的な金額を示すのに対して、金利というのは貸し借りされた金額に係る割合のことを示しています。例えば、100万円を借りて1年後に110万円返済する場合、利息は10万円で金利は10%となります。
利息制限法とは?
利息制限法は、債務整理に深く関係する法律の1つです。この法律と貸金業法、そして出資法の3つを合わせて、貸金三法といいます。
利息制限法は、債務者に当たる消費者を保護するための法律です。貸主が過剰な金利を設定して貸し付け、消費者を搾取することがない様に、貸し付けの際の金利の上限を定めています。その上限を超える金利で貸し付けることは、禁止されています。また、返済が遅れた際はその日数分の遅延損害金が生じるのですが、これについても上限が定められています。金銭の貸し借りに関する契約は、金銭消費貸借契約といいます。利息制限法は、この契約に関して上限を定めたものです。
基本的に、貸主と消費者の力関係は貸主が強く、消費者は弱いものです。そのため、元々は貸主が定めた金利に逆らうことはできませんでした。その結果、社会問題にもなっていたのです。その状況を是正するために、貸主の力を制限して消費者を守ろうと制定されたのが、利息制限法です。
利息制限法の上限金利は?
利息制限法 第1条
金銭の消費貸借の利息は、次の利率を超える部分は無効とする
①元本が10万円未満 年利20.0%
②元本が10万円以上100万円未満 年利18.0%
③元本が100万円以上 年利15.0%
利息制限法では、元本の額によって制限利率が異なっていて、元本額が大きいほど制限も大きくなります。
貸金業者からの借金は、同じ貸金業者から複数の契約での借り入れをしていた場合は、借入元本額を合計したものを基準とします。
遅延損害金の上限金利は?
遅延損害金については、以下のように定められています。
利息制限法 第4条
1、金銭を目的とする消費貸借上の債務不履行による賠償額の予定は、その元本に対する割合が第1条の規定の率の一・四六倍を超える場合、超過分は無効とする
2、違約金は前項の規定の適用に関して賠償額として扱う
利息制限法 第7条
第四条第一項の規定に関わらず、消費者金融等の営業による債務不履行によって生じる賠償額の予定については、その元本に対する割合が年利20%を超える部分については無効とする
遅延損害金は、利息制限法で定められた利息の制限の1.46倍が上限となっています。また、貸金業者からの借り入れに対する遅延損害金は、元本額に関わらず全て年利20%が上限となっています。
利息制限法による引き直し計算の例
過去に利息制限法の上限金利を超える金利で借り入れをしていた場合、引き直し計算によってその借金を減額し、場合によっては過払い金として返還請求ができることもあります。その計算は、どのようにして行われるのでしょうか?計算例について、解説します。
年利26%で50万円借りて、利息のみ返済を続けていた場合
利息制限法の上限金利では、借入額が50万円であれば年利18%です。その場合、以下のように変化します。
| 年利26%の場合 | → | 年利18%の場合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払額 | 利息 | 残元本 | 支払額 | 利息 | 残元本 | |
| 10,685円 | 10,685円 | 500,000円 | 10,685円 | 7,397円 | 496,712円 | |
| 10,685円 | 10,685円 | 500,000円 | 10,685円 | 7,349円 | 493,376円 | |
| 10,685円 | 10,685円 | 500,000円 | 10,685円 | 7,299円 | 489,990円 | |
| 10,685円 | 10,685円 | 500,000円 | 10,685円 | 7,249円 | 486,554円 | |
| 10,685円 | 10,685円 | 500,000円 | 10,685円 | 7,198円 | 483,068円 | |
| 10,685円 | 10,685円 | 500,000円 | 10,685円 | 7,147円 | 479,529円 | |
| ⋮79回目の返済 | ⋮ | ⋮ | ⋮79回目の返済 | ⋮ | ⋮ | |
| 10,685円 | 10,685円 | 500,000円 | 10,685円 | 195円 | 2,702円 | |
| 10,685円 | 10,685円 | 500,000円 | 10,685円 | 40円 | -7,943円 |
上記のように支払っていた場合、元々は利息分しか返済していないので元本は減りませんでした。しかし、上限金利で引き直し計算をすると、6年8カ月で完済して過払い金が発生していました。それ以降の返済分は、全て過払い金となります。
年利23%で当初10万円を借りて、1年後に50万円に増額、その後ずっと利息のみ返済
この場合、過去の支払い分については金利が変わらないものとして考えます。10万円以上なので、上限金利も18%のままとなります。
| 年利23%の場合 | → | 年利18%の場合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払額 | 利息 | 残元本 | 支払額 | 利息 | 残元本 | |
| 1,890円 | 1,890円 | 100,000円 | 1,890円 | 1,479円 | 99,589円 | |
| ⋮1年間継続 | ⋮ | ⋮40万円増額 | ⋮1年間継続 | ⋮ | ⋮40万円増額 | |
| 9,452円 | 9,452円 | 500,000円 | 9,452円 | 7,397円 | 493,008円 | |
| 9,452円 | 9,452円 | 500,000円 | 9,452円 | 7,367円 | 490,850円 | |
| 9,452円 | 9,452円 | 500,000円 | 9,452円 | 7,336円 | 488,660円 | |
| 9,452円 | 9,452円 | 500,000円 | 9,452円 | 7,305円 | 486,437円 | |
| ⋮累計113回目の返済 | ⋮ | ⋮ | ⋮累計113回目の返済 | ⋮ | ⋮ | |
| 9,452円 | 9,452円 | 500,000円 | 9,452円 | 215円 | 5,310円 | |
| 9,452円 | 9,452円 | 500,000円 | 9,452円 | 79円 | -4,063円 |
この場合は、最初の1年間を含めて9年6カ月目で過払い金が発生します。
年利24%で50万円借りて毎月約定の17,000円ずつの返済を継続
途中で追加の借り入れをせず、毎月17,000円ずつ返済した場合は、以下のようになります。
| 年利24%の場合 | → | 年利18%の場合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払額 | 利息 | 残元本 | 支払額 | 利息 | 残元本 | |
| 17,000円 | 9,863円 | 492,863円 | 17,000円 | 7,397円 | 490,397円 | |
| 17,000円 | 9,722円 | 485,585円 | 17,000円 | 7,255円 | 480,652円 | |
| 17,000円 | 9,579円 | 478,164円 | 17,000円 | 7,111円 | 470,763円 | |
| 17,000円 | 9,432円 | 470,596円 | 17,000円 | 6,965円 | 460,728円 | |
| ⋮39回目の返済 | ⋮ | ⋮ | ⋮39回目の返済 | ⋮ | ⋮ | |
| 17,000円 | 2,007円 | 101,745円 | 17,000円 | 221円 | -1,834円 | |
| ⋮44回目の返済 | ⋮ | ⋮ | ⋮44回目の返済 | ⋮ | ⋮ | |
| 17,000円 | 469円 | 7,232円 | 10,700円 | -1,037円 | -89,526円 | |
| 7,375円 | 143円 | 0円 | 10,685円 | -1,325円 | -98,226円 |
上記のように、24%の金利で計算した場合は完済まで45回の返済が必要ですが、上限金利の18%で計算した場合は39回目の返済ですでに完済することになるため、残りは過払い金となります。その場合、45回目には10万円近い過払い金が発生しているのです。
利息制限法の上限金利を超えた契約はどうなる?
今ではまずいなくなりましたが、かつては利息制限法の上限を超える金利で貸し付けていた貸金業者はたくさんいました。その契約は、どのような扱いになるのでしょうか?
超過分は無効だが、罰則は認められていない
よく、法律違反の金利で貸し付けていたのだから契約は無効であり、返済の必要はないと思っている人がいます。しかし、実は契約がすべて無効となるわけではないので、当然ながら返済する必要はあるのです。ただし、その際は利息制限法を超えている金利分は無効となります。そのため、無効になる分を計算し直して、払いすぎていた分を過払い金として取り戻すことができるのです。
例えば、150万円を年利21%で借りていたとします。その場合、利息制限法で定められている上限金利は15%なので、上限金利を超えています。だからといって、その借金は返済しなくてもいい、ということにはなりません。その上限金利を超えている、6%分だけが無効となるのです。
とはいえ、これまでの返済額から6%分ずつ引いていけばいい、というわけではありません。同じ返済額で金利分が減るということは、その分を元本の返済に使うことになります。そうなると、翌月分は過去の計算より利息が減ります。そうなると、元本の返済として扱われる額はさらに増えるのです。それを計算し直すのが、引き直し計算です。計算の結果、借金の額がかなり減額され過払い金が発生していることもあるので、計算はなるべく専門家に依頼したほうがいいでしょう。
では、上限を超える金利で貸し付けていた貸金業者には、どのような罰則があるのでしょうか?実は、特に罰則はないのです。かつてのグレーゾーン金利での貸し付けが行われていた時は、利息制限法に違反しても刑事罰の対象とはならず、出資法に違反した場合のみ刑事罰があったのです。そのため、多くの貸金業者は年29.2%までの金利なら問題はない、と考えていました。
しかし、その後貸金業法が改正されたことで、行政指導や刑事罰などの対象になりました。また、出資法の上限金利も年利20%までに引き下げられています。
出資法や貸金業法によって罰則があることも
かつて、出資法で定められていた上限金利は年利29.2%でしたが、現在は法律が改正されて出資法でも上限金利は20%になりました。それを超える金利で貸し付けをすると、刑事罰の対象となります。具体的な罰則としては、金融業者であれば3000万円以下の罰金か10年以下の懲役、もしくはその両方を科されます。金融業者以外であれば、1000万円以下の罰金か5年以下の懲役、もしくはその両方です。
また、貸金業法違反としても行政指導を受ける必要が生じるかもしれません。その場合、貸金業者としての登録の取り消し、あるいは業務停止命令が出されることがあります。
法改正前の金利は変わらない点に注意
法律が変わって上限金利が引き下げられた場合でも、法律が改正される前に締結されている貸付契約については、その金利が下がることはありません。新たに契約を結んだ場合は利息制限法に基づいた金利となるのですが、元々それを超える金利で契約していれば金利が自動的に下がるということはありません。
利息制限法の改正で以前と変わった点は?
利息制限法は、2006年に改正され2010年から施行されました。改正後は、依然とどのような点が変わったのでしょうか?変更された点について、解説します。
グレーゾーン金利が存在していた
以前の利息制限法では、現行法と同じ利率の上限金利が定められていました。しかし、それには続いて、上限金利を超える金利を任意に支払った場合、その規定にかかわらずその返還を求めることはできない、とされていました。つまり、その金利を承知したうえで支払っていた場合は、それを無効にすることができなかったのです。
また、金利を定める法律にはこれ以外にも、出資法がありました。出資法では貸付金額に関わらず、年利29.2%を上限としていたのです。そして、利息制限法は違反しても特に罰則はないのですが、出資法に違反した場合は刑事罰が科されていました。そのため、多くの貸金業者では出資法に違反しない程度の高金利に設定していたのです。この2つの法律の間にあたる金利を、グレーゾーン金利といいます。
みなし弁済が根本の原因だった
グレーゾーン金利が横行していた原因となったのが、みなし弁済という制度です。これは、一定の要件を満たしていれば、本来は無効となる利息制限法の上限金利を超える金利の返済分を、貸金業者が正規に受領することができるとしていたものです。その要件は、旧貸金業法の台43条に定められていました。
当時も、過払金という考え方はありました。しかし、このみなし弁済として認められてしまうと、過払金として請求することもできなくなるのです。その要件としては、貸金業者が貸金業登録をしていること、貸し付けの際は所定の条件を満たした書面を交付していること、利息を借主が自分の意志で支払っていることなどです。ほとんどの場合は、この要件を満たしているでしょう。
このみなし弁済という制度があったせいで、利息制限法はその意味をほとんど持たない法律となってしまいました。裁判の際も争点となることが多かった点で、認められていたのはごく一部だけです。ほとんどの場合は、厳密にはその要件を満たしていないと解釈されて適用できないとされていたのです。しかし、みなし弁済という制度そのものを知らない人もたくさんいて、そういった人たちは裁判まで至らなかったのです。
法改正によってグレーゾーン金利が撤廃された
利息制限法や貸金業法などが改正されたことで起こった変化のうち最も大きいものは、グレーゾーン金利が撤廃されたということでしょう。改正後は、利息制限法の上限金利を超える金利は絶対的に無効となることが定められたので、違反をする意味がなくなったのです。また、それは過去にさかのぼって適用されるので、これまでの返済分でも上限金利を超えている部分があれば、引き直し計算ができるようになりました。そして、返済を完了している状態で余分に支払っていた分がある場合は、過払金として返還請求ができるようになったのです。
ただし、利息制限法に違反したとしても、刑事罰の対象にはなりません。出資法違反として刑事罰が科されたり、貸金業法違反として行政指導の対象となったりすることはありますが、利息制限法違反として罰せられることはないのです。
借金問題は専門家に相談しよう
借金問題を解決したいのであれば、債務整理をしましょう。そして、債務整理の手続きをするのであれば、借金問題の専門家である司法書士や弁護士に依頼するのがおすすめです。専門家に依頼するメリットや、必要となる費用について解説します。
専門家に依頼するメリット
借金問題の解決を専門家に依頼した場合、まず返済がストップします。また、滞納していて督促などを受けている場合も、督促が停止するのです。専門家に依頼した時点で債権者には受任通知が送付され、それ以降の借金関係の窓口は専門家になるからです。
また、借金問題を解決するための債務整理には、様々な法律の知識が必要となります。自分でその手続きをするにはかなりの手間がかかってしまい、時間もかかるでしょう。しかし、専門家に依頼すればその手続きの大部分を代わりにやってもらうことができます。専門家であれば、確かな知識に基づいて手続きをスムーズに進めることが可能です。そのため、最小限の時間で借金問題を解決することができるでしょう。
専門家に依頼する場合の費用
専門家に借金問題の解決を依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのかが気になる人もいるでしょう。専門家には主に弁護士と司法書士がいるのですが、基本的に弁護士よりも司法書士の方が費用は安くなっています。
また、債務整理をする場合は任意整理と個人再生、自己破産があります。どの手続きをするかによっても、費用は変わってくるのです。
司法書士に任意整理を依頼した場合、相談料などは無料という所もあります。基本報酬として1社あたり、2~5万円ほどかかり、さらに減額出来た場合はその金額の10~20%ほどが成功報酬となります。
個人再生の場合、裁判所に申立をして手続きを行います。その場合に専門家へと支払う費用は、おおよそ42万円~です。
自己破産も、裁判所に申立をして行う手続きです。その手続きのうち、同時廃止になった場合は専門家に35万円~支払う必要があります。小額管財の場合は、それに加えて22万円、合計55万円ほど必要になります。管財事件になるとさらに増えるので、気を付けましょう。
まとめ
・利息制限法は、金銭消費貸借における金利の上限を定めた法律
・上限金利は、借り入れる金額によって異なる
・借入金額が10万円未満の場合、上限金利は20%となる
・借入金額が10万円以上100万円未満なら、上限金利は18%
・100万円以上の場合は、15%が上限となる
・借入金額は、貸金業者ごとの合計借入額のこと
・1契約ごとではない
・過去に上限金利以上の金利で返済をしていた場合は、引き直し計算で正確な額を把握する
・過剰に支払っていた分がある時は、過払金として返還請求ができる
・上限金利を超える金利分は、無効となる
・利息制限法に違反した場合も、特に罰則はない
・出資法や貸金業法に違反していれば、罰則を与えられることもある
・利息制限法が改正されるまでは、グレーゾーン金利で貸し付けられることが多かった



























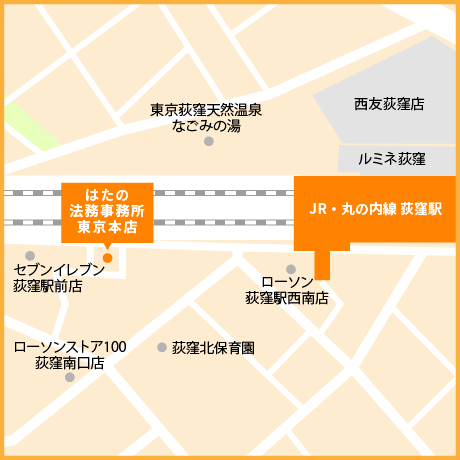
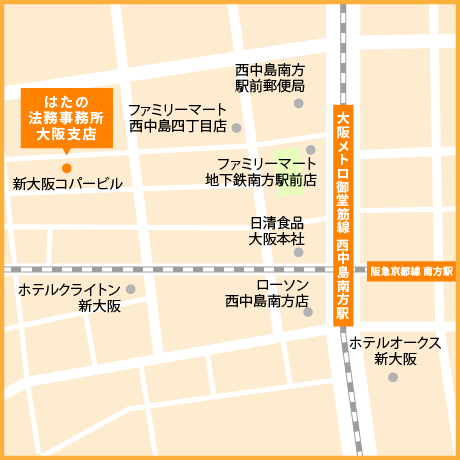







クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。